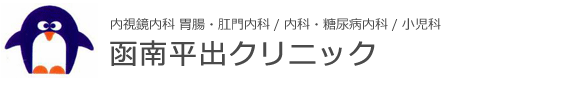- ホーム
- RSウイルス感染症
RSウイルス感染症
RSウイルス感染症
RSウイルス感染症とは
RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)は、乳幼児を中心に流行する呼吸器感染症のウイルスです。毎年、秋から冬にかけて流行し、生後6か月以内の赤ちゃんや基礎疾患を持つ子どもでは重症化することがあります。
2歳までにほぼすべての子どもが一度は感染するとされるありふれたウイルスですが、重症化するケースもあるため、特に乳児では注意が必要です。
RSウイルスの主な症状
2歳までにほぼすべての子どもが一度は感染するとされるありふれたウイルスですが、重症化するケースもあるため、特に乳児では注意が必要です。
RSウイルスの主な症状
感染初期は風邪に似た症状から始まります。
- 鼻水
- 咳
- 発熱(38〜39℃程度)
- 食欲低下
- 呼吸が速い、ゼーゼー音(喘鳴)
多くの場合は軽症で済みますが、「細気管支炎」や「肺炎」へと進行し、呼吸困難・哺乳不良・無呼吸発作などがみられることがあります。これらの症状が出現した場合は、入院が必要となるケースもあります。特に生後6か月未満の乳児で重症化するリスクが高いとされています。
感染経路と流行時期
RSウイルスは、飛沫感染および接触感染により広がります。咳やくしゃみの飛沫、ウイルスが付着した手指やおもちゃなどを介して感染します。感染力が強く保育園や家庭内での兄弟間感染が多く見られます。
近年では、従来の秋〜冬に加えて夏季にも流行が見られるようになっており、季節に関係なく注意が必要です。
診断と検査
近年では、従来の秋〜冬に加えて夏季にも流行が見られるようになっており、季節に関係なく注意が必要です。
診断と検査
RSウイルスは、鼻咽頭ぬぐい液を用いた迅速抗原検査で診断が可能です。乳児や症状の強い小児では、発熱や咳が長引く場合に検査を行うことがあります。ただし、明確な治療薬がないため、検査の実施は重症度や年齢、同居家族の状況などを総合的に考慮して判断します。
治療法
RSウイルスに対する特効薬はなく、対症療法が中心です。ご家庭では水分の摂取や鼻汁の吸引を行ってください。呼吸を楽にするために吸入器の貸し出しなども行います。軽症であれば自宅で経過観察が可能ですが、以下のような場合は医療機関での処置や入院が必要になることがあります。
- 呼吸が苦しそう(陥没呼吸、鼻翼呼吸)
- 授乳ができない、ミルクの飲みが悪い
- ぐったりしている
- 無呼吸の既往がある
- 酸素飽和度(SpO₂)が低下している
入院治療では、酸素投与、点滴、吸引などを行いながら全身管理を行います。
予防法
RSウイルス感染症には有効なワクチンは存在しません(2025年時点)。そのため、感染予防には日常生活での工夫が非常に重要です。
- 手洗い、手指消毒の励行
- 咳エチケット(マスク着用)
- 兄弟が保育園などから帰宅した際の手洗い・衣類交換
- 人混みを避ける
- 体調不良の人との接触を避ける
特に新生児や早産児、心疾患・肺疾患をもつ乳児に対しては、RSウイルスの発症や重症化を防ぐために「パリビズマブ(シナジス)」というヒト化モノクローナル抗体の投与が行われる場合がありますが、これはワクチンではなく、月1回の筋肉注射によってウイルスへの免疫力を一時的に高める方法です。
再感染と注意点
RSウイルスは一度感染しても免疫が不完全なため、何度でも再感染します。ただし、年齢が上がるにつれて症状は軽くなる傾向にあり、再感染時は軽い鼻風邪程度で済むことが多くなります。
ただし、高齢者や基礎疾患のある成人では、再感染でも肺炎を起こすことがあるため、家族内に感染者が出た場合は注意が必要です。
当院での対応
ただし、高齢者や基礎疾患のある成人では、再感染でも肺炎を起こすことがあるため、家族内に感染者が出た場合は注意が必要です。
当院での対応
当院では、RSウイルスの迅速検査に対応しております。治療は対症療法が基本となりますが、鼻汁の吸引や吸入療法など必要に応じて行います。肺炎・中耳炎の合併も多くRSウイルス感染以外の症状に対して治療を必要とすることがあります。必要に応じて紹介も行います。
ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
- ホーム
- 小児科案内
- 小児科診療予約のご案内
- 乳幼児健診について
- 病児保育のご案内
- 内視鏡内科 / 胃腸・肛門科案内
- 内科・糖尿病内科案内
- 予防接種について
- 子どもの疾患
- 行政の補助について(小児科)
- 施設基準の告知について
- お問い合わせ・交通アクセス
- リンク集
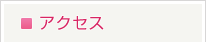
- 〒419-0124
静岡県田方郡函南町塚本952-24 [地図] - TEL: 050-3189-4004
 駐車場あり
駐車場あり
アクセス数:1109887